オランダ輸送ガイド|ロッテルダム港トランジットとEU再通関
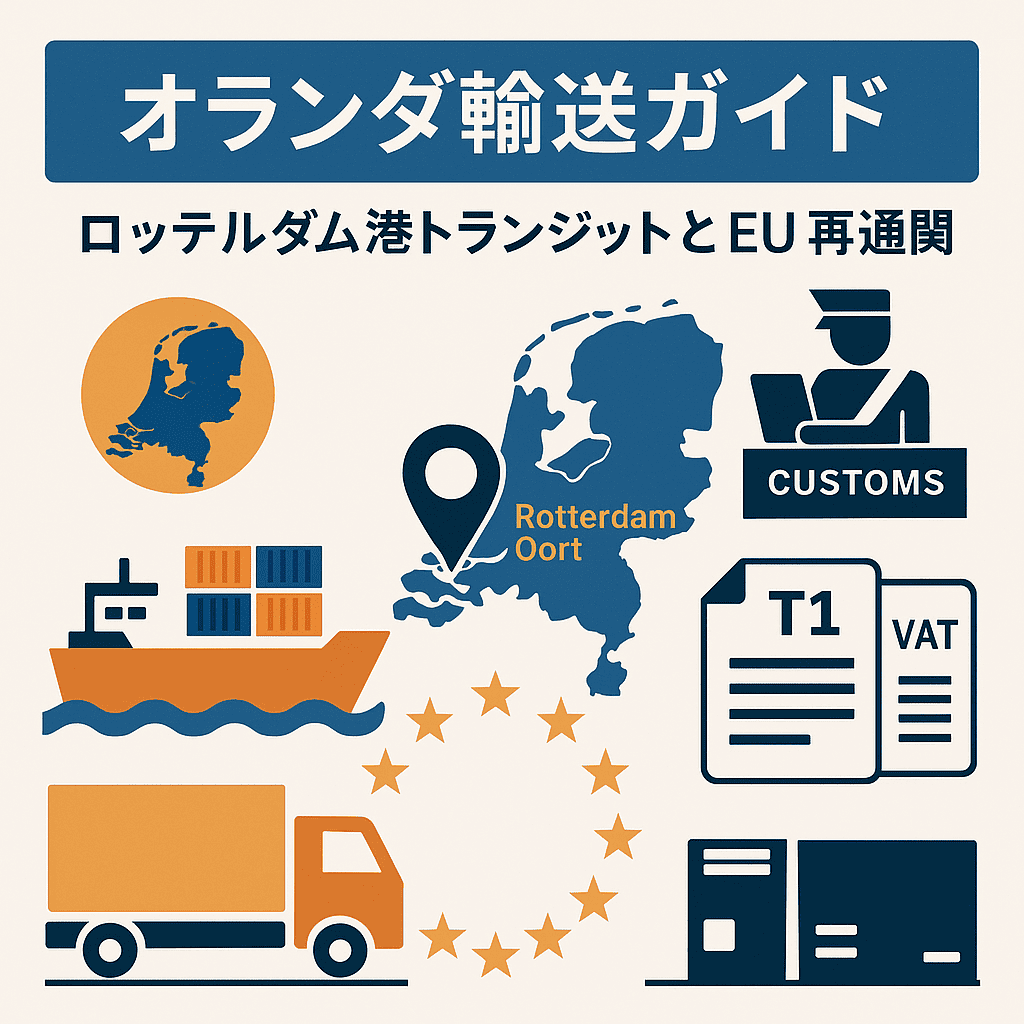
なぜロッテルダム港が”EUの玄関口”なのか
ロッテルダム港は年間約4.5億トンの貨物を取り扱う、ヨーロッパ最大かつ世界有数の港湾です。
EU共通市場における最初の通関地として、ロッテルダムでの輸入申告や税務処理は、EU全域への物流効率を大きく左右します。日本からの輸出貨物でも、最初にオランダ経由を選ぶ企業が多いのは、通関の迅速さと安定したコスト構造があるためです。
ロッテルダムは航空輸送&内陸水路も強い
また、ロッテルダムは海上輸送だけでなく、航空貨物や内陸水路(バージ船)にも強く、EU内陸部への接続性が高い「総合ハブ」としての役割を担っています。EU輸送を考える際、この港を起点とした通関・トランジット戦略を理解します。
よくある誤解:「EU内だから通関不要」は間違い
EU加盟国間では貨物の自由な移動が基本ですが、実は最初にEU圏へ入る国(オランダなど)で輸入申告(T1/T2)をすることが義務付けられています。この手続きを怠ると、EU域内の再通関やVAT処理に大きな影響を与えます。
ロッテルダム港で頻発するトラブル
特にロッテルダム港では、MRN(Movement Reference Number)番号の不一致や記載ミスにより、貨物が保留または通関停止になる事例が頻発しています。保税倉庫での滞留が長引けば、所有権移転や保管料増加のリスクも発生します。
再通関やVAT(付加価値税)の処理が遅れると、EU内での取引が一時停止し、商流全体に影響を及ぼすこともあります。そのため、通関後の税務処理までを見越した体制設計が必要です。
日本→ロッテルダム→EU各国のトランジットモデル
オランダ経由輸送の典型的な流れは、以下の通りです。
- 日本から輸出(NACCSで輸出書類作成)
- ロッテルダム港で輸入申告・T1書類発行
- ドイツ・フランス・ベルギーなどEU各国へ再輸送(再通関含む)
この際、NACCSなどで作成した輸出書類をオランダ側の輸入者やフォワーダーに正確に共有し、MRNコードを発行・追跡することが重要です。

T1書類は最終通関まで必ず保管し、C88(申告書)への転記を行いましょう。
オランダ保税倉庫・再通関の正しい使い方
ロッテルダムでは保税倉庫を活用することで、EU域内または域外への再輸出が柔軟に行えます。貨物を一時保管し、仕向け国や販売先が決まり次第、再通関・再出荷することで、在庫リスクを最小化できます。
オランダ独自のVAT制度を活用する
オランダには「Deferred VAT system(繰延VAT制度)」があり、輸入時にVATを一時的に免除する仕組みがあります。
加えて「Article 23 licence(VAT免税ライセンス)」を取得した企業は、輸入時のVAT支払いを完全に免除され、現金フローを大幅に改善できます。
これらの制度を正しく運用するには、現地通関業者(Douane)や税理士との連携が不可欠です。
UCCとオランダ通関制度の特徴は、こちらの記事で詳しく解説しています。
電子通関システム(NCTS・ICS2)の具体運用とトラブル対処
NCTS(新共通通過制度)やICS2(貨物情報事前申告制度)は、トランジット貨物を含むEU輸送全体で重要な役割を担います。
しかし、実務ではシステム間通信エラーやMRN重複登録など、さまざまなトラブルも発生します。
トランジット貨物の保険契約と請求実務
オランダ経由のトランジット貨物では、保険契約条件の明確化が必要です。中間国を経由するため、保険責任の分散が起こりやすく、契約時に補償範囲を明文化します。
特に「戦争危険除外条項」や「遅延補償特約(Delay Clause)」などの条件は、EU内の鉄道・トラック輸送でも重要です。
保険金請求
保険金請求の際には、MRN番号・輸送経路・税関記録を証拠書類として提示できるよう管理することがポイントです。より詳しい補償範囲・請求手順については、「EU貨物保険とリスク管理の実務」記事で扱っています。
フォワーダー選定と評価基準チェックリスト
ロッテルダム経由輸送を成功させるには、通関・税務処理に強い現地フォワーダーの選定が欠かせません。以下の観点で評価するようにしましょう!
- NCTS・ICS2など電子通関システムに精通しているか
- VAT免税制度(Article 23)に関する実務経験があるか
- MRN・T1管理ツールを用いて貨物追跡が可能か
- トランジット貨物に関する保険・税務トラブル対応の実績があるか
- 日本側との時差・言語対応フローが整備されているか
これらを確認するためのフォワーダー評価チェックリストは、「ヨーロッパフォワーダー選定ガイド」でダウンロードできます。
貨物管理支援ツールと情報共有の高度化
EU輸送では、MRN管理や書類共有を効率化するためのITツール導入が進んでいます。
特に、クラウド上でMRN番号・税関申告・VAT処理を一元管理できる物流管理プラットフォーム(例:Portbase、CargoSmartなど)が有効です。
日本企業でも、NACCSデータを自動連携させることで、ロッテルダム港での輸入申告や再通関のタイムロスを削減できます。詳細は「EU物流DX・デジタル管理ツール特集」で紹介しています。
VAT・税務リスクを防ぐ3つのポイント
オランダ経由輸送で税務リスクを回避するためには、以下の3点を徹底しましょう。
1.T1・MRN書類を確実に管理する
通関番号や貨物情報の一致を常に確認します。
2.VAT免税/還付処理は専門家と連携する
現地通関業者または税理士との二重チェックを徹底します。
3.再通関時に書類を分ける
UCC基準に基づき、原本を保存し誤記リスクを防止します。
これらの手続きを怠ると、貨物の出庫停止や課税リスクが発生します。特に日本企業がEUへ初めて輸出する際は、フォワーダー側に通関・税務連携の責任範囲を明確化しておくことが重要です。
オランダ経由輸送を成功させる実務チェック
実務で確認すべきポイントを以下にまとめます。
- NACCSとオランダ税関(Douane)の電子申告システム連携を確認する
- T1・MRN番号を確実にフォワーダー側で追跡・保存する
- VAT免税(Article 23 licence)や還付制度の適用有無を事前確認する
- 保税倉庫利用時は貨物保険と倉庫契約条件(移転リスク)を明文化する
最後に、オランダ経由輸送を最適化するには、再通関と税務処理の両方に強い現地フォワーダーの存在が不可欠です。電子申告、VAT管理、保税倉庫ネットワークを一元的に扱えるパートナーを選ぶことで、物流全体のスピードと安全性が大幅に向上します。
まとめ:ロッテルダム経由輸送を成功させるには
ロッテルダム経由のEU輸送を成功させるには、電子通関、税務処理、トランジット管理を総合的に理解することが不可欠です。
日本企業はNACCSと欧州電子通関システムを連携させ、MRN追跡・VAT処理・保険契約を一体で管理する仕組みを構築すべきです。これにより、物流スピードと透明性が向上し、EU市場全体での競争力を高めることができます。



