EU通関制度(UCC)の実務対応|前倒し審査と再通関の基礎
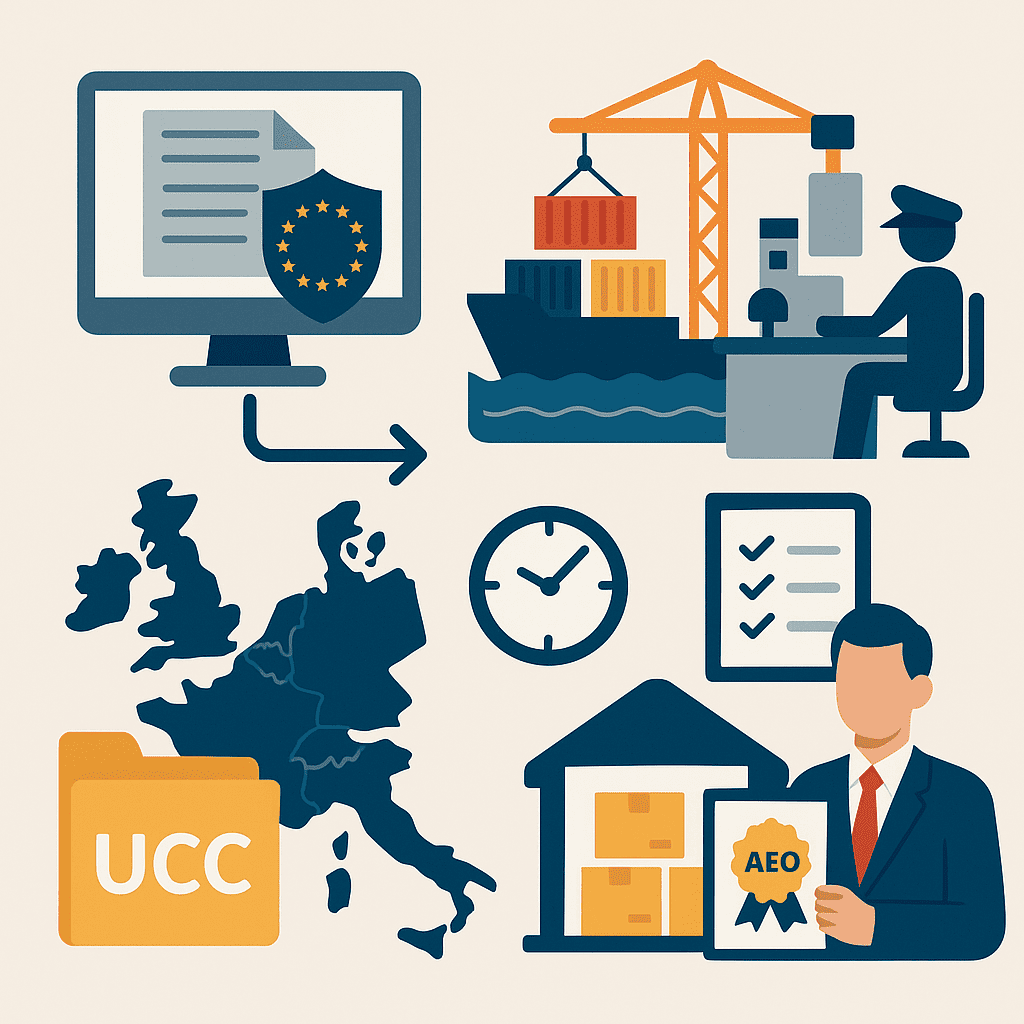
EU通関制度「UCC」とは?
UCC(Union Customs Code)は、EU全域の通関および貿易管理を統一する制度で、2016年に全面施行されました。
この制度により、EU加盟国は共通のルールに基づいて輸出入手続きを行うことになり、電子申告の義務化やリスク管理の強化が進められています。
ドイツ(Zoll)やオランダ(Douane)など各国税関は、UCCを基準に運用を行いながらも、国ごとに独自の手続きがあります。
日本企業にとっても、EPAの適用、再通関、VAT処理などがこの制度の下で行われるため、UCCは輸出入実務に直接、大きな影響を与えます。
本記事では、UCCの実務的なポイントとして「前倒し審査」「再通関」「AEO制度」の3つを中心に解説します。
UCCとオランダ通関制度の特徴
UCC(Union Customs Code)は、EU全体の通関ルールを統一する法制度です。その中でも、オランダ税関(Douane)はUCCの運用を最も早く電子化した国の一つであり、e-Declarationやe-Transitによる自動申告システムを採用しています。

これにより、貨物の申告からMRN発行、トランジット完了までが電子的に追跡可能になっています。
ロッテルダム港の重要性
ロッテルダム港はEU全体の輸入貨物の約20%を扱っており、EU物流の中心地です。また、オランダ税関が発行する公式ガイド「Customs Transit Procedures in the Netherlands」は、申告・再通関の標準手順として実務の基準となっています。
よくある誤解と実務での困難
UCCは統一制度ですが、実際の運用は国によって差があります。
例えば、オランダでは通関が完全電子化されている一方で、南欧の一部国では紙書類の提出を併用しています。このため、書類審査のスピードや運用ルールに差が生じています。
再通関とトランジット貨物の落とし穴
再通関やトランジット貨物に関しては、「MRN番号」や「申告種別」の記載ミスが原因で貨物が保留されるケースが多く見られます。
特にEU域内の再輸送では「通関不要」と誤解して申告を怠り、課税トラブルに発展する事例もあります。
さらに、申告書(C88)とトランジット書類(T1/T2)の違いを理解していないことで処理が複雑化し、輸送遅延を引き起こすケースもあります。これらの誤解を防ぐためには、UCC制度と国別の実務運用を正確に把握しておくことが必要です。
実務者が押さえるべきUCC対応の3ステップ
ここからは、実務で必ず押さえておくべき3つのステップを解説します。
ステップ1:電子通関システムの前倒し運用
輸入貨物の到着前に通関審査を完了させる仕組みが「前倒し審査(Pre-declaration)」です。NCTSやICS2では、到着24〜48時間前に電子データを送信し、リスク評価を先行実施できます。
操作の流れ(概要)
- NACCSまたはERPシステムで輸出データ作成
- オランダ税関(Douane)にXMLフォーマットで送信
- MRN発行 → EU ICS2に自動連携
- “Accepted”表示後に積込許可
エラー表示(例:「Data Set Error」「Invalid MRN」)が出た場合は、再送信が必要です。こうしたトラブル対処やシステム別操作マニュアルについては、「EU電子通関トラブル対策ガイド」で詳しく解説しています。
ステップ2:トランジット手続きと再通関の整理
再通関では「T1書類を閉鎖し忘れた」「C88に誤って他国MRNを記載した」などの人為ミスが多く、貨物が保税倉庫で滞留することがあります。
成功事例と失敗事例
成功例としては、フォワーダーとクラウドでMRN進捗を共有し、到着48時間前に再通関データを仮登録しておく事例があり、リードタイム短縮に寄与しています。
一方で失敗例やベストプラクティスについては、「再通関ケーススタディ集(別記事)」で補足していますので、ぜひご参照ください。
ステップ3:認定事業者(AEO)制度の活用
AEO(Authorized Economic Operator)制度は、信頼性の高い事業者として税関に認定される制度です。
取得までの流れ
- 申請書提出(税関当局へ)
- 内部管理・安全体制の審査
- 認定証交付(通常6〜12か月)
更新時の注意点
AEO認定は5年ごとに再審査があり、内部統制・記録保存体制の確認が行われます。また、人事異動や組織変更で責任者が変わる場合には、再届出義務があります。
AEO認定を維持する企業は「簡略通関」「優先審査」の恩恵を継続的に受けられます。これらの詳細フローは「AEO認定実務ガイド」で解説しています。
社内マニュアルと教育の実務化
UCC対応を社内に定着させるには、部署横断の教育が必要です。通関・物流・経理が共通で利用できる「UCC実務マニュアル」を整備し、次の項目を明確にしましょう。
- 通関書類(C88・T1)の作成・承認フロー
- ICS2申告手順の社内標準化
- 税関問い合わせへの一次対応マニュアル
- 新人向け教育プログラム(e-ラーニングや演習形式)
社内教育プランのサンプルは「EU通関教育モデル集」で紹介しています。
電子通関連携とITサポート体制
電子通関では、IT連携が不可欠です。
NCTS・ICS2と自社ERP・NACCSを結ぶインターフェースでは、データフォーマットやタイムゾーンの違いによる通信障害が発生することがあります。
そのため、社内IT部門と通関担当の定例連絡網を構築し、障害発生時に再送信・再審査を即座に実行できる体制を整えます。
制度条文・欧州委員会資料・実例
UCCの法的根拠は、Regulation (EU) No 952/2013および関連するDelegated Actsにあります。特に次の条文が実務上で重要です。
- 第16条:電子申告の義務化
- 第19条:事前審査(Pre-declaration)
- 第36条:リスク管理と安全審査
欧州委員会の公式情報
欧州委員会のTaxation and Customs Union(TAXUD)が運営する公式ポータルでは、UCC Work ProgrammeおよびICS2フェーズ2の進捗状況が公開されています。これにより、加盟国全体の通関電子化が段階的に進んでいることが確認できます。
日本企業の成功事例
日本企業の事例では、自動車部品輸出においてEPAとUCCを組み合わせることで、通関前倒しによるリードタイム短縮を実現したケースも報告されています。
まとめ:EU通関を安定させる5つの実務対策
EU通関を安定的に運用するためには、以下の5つの実務対策を徹底しましょう。
- Pre-declaration運用を標準化(到着48時間前申告で通関前倒し)
- 再通関時の書類管理を徹底(MRNとC88の整合性確認)
- AEO認定企業との協働(優先審査でリードタイム短縮)
- 社内マニュアル・教育の常設化(担当者交代でも継続運用)
- IT連携とトラブル即応体制(通信障害に備えた再送ルール)
UCC制度を正しく理解し、前倒し審査と電子通関の両輪で運用することが、EU物流を安定化させる第一歩です。
トラブルから探す
次に確認すべき整理先
書類不備や条件の違いで止まっており、どこまで直すべきか分からない場合は、以下の記事で判断と作業を分けてください。
👉書類不備で止められている方へ|今、自社で判断できる状態か整理する



