ドイツ輸送の実務ガイド|EPA・原産地証明と鉄道輸送の実際
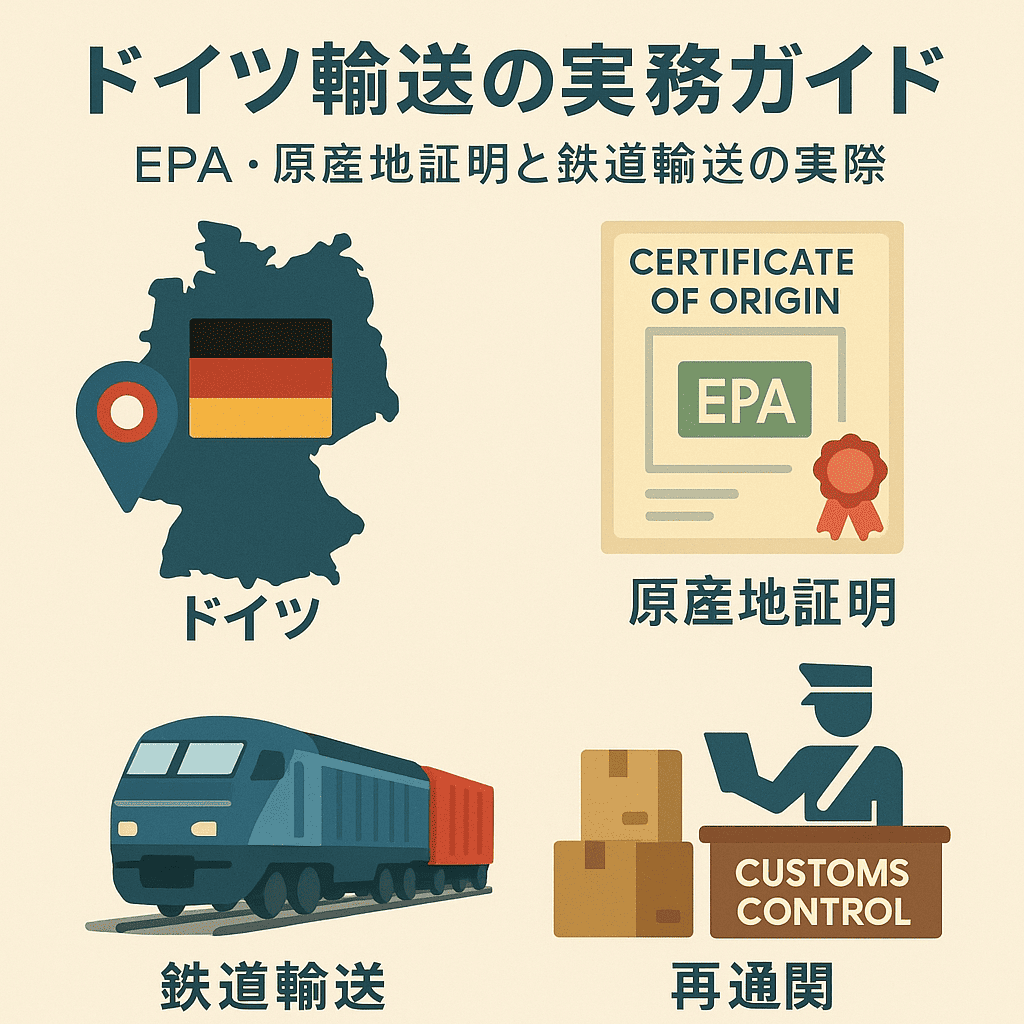
ヨーロッパ最大の物流拠点、ドイツ輸送が”特別扱い”される理由
ドイツはヨーロッパの物流の中心であり、ハンブルク港、フランクフルト空港、そしてデュイスブルク鉄道ターミナルを擁する世界有数の輸送拠点です。
陸続きという地理的優位性を生かし、ポーランド、オランダ、中国などの周辺国からの鉄道・陸送ルートも急速に発展しています。その結果、日本企業のドイツ向け輸出では、EPAの適用、再通関、VAT処理などが複雑に絡み合う構造になっています。
さらに、EUの制度統一を支えるUCC(Union Customs Code)と、環境政策である「Green Deal」の双方が、ドイツの物流に大きな影響を与えています。
本記事では、EPA活用の正確な理解と鉄道輸送の現実的な運用を軸に、実務で失敗しないためのポイントを整理します。
よくある誤解:原産地証明を”EPA利用=自動的に関税ゼロ”と捉えている
日EU・EPAを活用すれば、原則として関税優遇を受けられます。しかし、「原産地証明書を提出すれば自動的に関税ゼロになる」と誤解しているケースが非常に多いです。実際には厳格な条件を満たさないと適用されません。
自己申告と特定原産地証明の違い
特に注意が必要なのは、自己申告(REX登録)と商工会議所発行の特定原産地証明では要件が異なり、保存義務や責任の範囲も変わる点です。
REX制度
REX制度では、原産地判定の根拠(製造工程・部材構成・HSコード照合表)を社内に5年以上保管し、税関監査時に提示できる体制が求められます。
監査対応では、輸出部門・経理部門・通関部門を横断した内部管理体制を構築し、監査担当者・文書保管者・輸送実績照合者などの役割分担を明確にしておくことが重要です。
輸送途中での再通関に注意
輸送途中で再通関が発生する場合(例:ロッテルダム経由)、HSコードの不一致やインボイス記載の誤りによってEPA適用が取り消されることもあります。EPA活用時は、証明書・インボイス・パッキングリストの整合性を必ず確認しましょう。
継続的な監査・更新業務が必要
監査・更新業務では、以下のような継続的な運用が求められます。
- EPA証明書の有効期限管理
- REX番号更新時の再登録申請
- 税関照会への即応体制
社内で監査チェックリストを整備し、異常があればフォワーダーと迅速に共有する仕組みがあると安心です。これらの詳細運用については「EPA監査対応ハンドブック(別記事)」で解説しています。
なお、鉄道輸送の場合は「ブロックトレイン」と「混載便」で求められる書類が異なり、通関やEPA証明の整合性を欠くと輸送全体が遅延するリスクもあります。
鉄道輸送の混載リスクと現地通関の落とし穴
鉄道輸送は環境負荷が低く、CO₂削減を目指すGreen Dealに沿った輸送手段として注目されています。ただし、実務面ではいくつかの注意点があります。
混載貨物では通関時のリスクが高まる
混載貨物では、通関時に貨物の識別が難しく、特にドイツ税関(Zoll)はEPA証明書の内容を厳格に審査します。貨物番号やHSコードにわずかなズレがあるだけでも、EPA適用が拒否されるリスクがあります。

VAT処理においても、申告地のずれやタイミングの違いによって還付が受けられない場合があるため、注意が必要です。
トレーサビリティシステムの進化
近年では、GPSやIoTセンサーによるトレーサビリティシステムの導入が進んでいます。デュイスブルクを中心に、貨物の位置・温湿度・衝撃をリアルタイムで監視できる仕組みが整備されつつあり、異常検知時にはフォワーダーが即座に対応可能です。
日本側でも輸出前にシリアル番号やロット管理を紐づけておくと、EPA証明や輸送モニタリングとの整合を取りやすくなります。
EPA申請と原産地証明の流れ
EPA申請を正確に行うためには、以下の流れを押さえておきましょう。
1. HSコードの正確な確認
製品仕様と関税分類を一致させることが第一歩です。HSコードの誤りは、後の工程すべてに影響します。
2. 原産地規則の判定
WO(完全生産)やCTH(関税分類変更)など、日EU協定で定められた基準を確認します。
3. 証明書の作成
自己申告(REX番号必須)または特定原産地証明(商工会議所発行)のいずれかを選択します。
4. 輸入国への提出・保存
輸入者側での記録保存期間(通常5年)を遵守することが求められます。
EPA利用時は、申告書・インボイス・パッキングリストにおける産地・数量・価格情報の整合性が特に重要です。少しでも不一致があると、ドイツ税関から修正指導や再審査を受ける可能性があります。
ドイツ向け輸送ルート選択:海上/航空/鉄道の使い分け
ドイツ向け輸送では、貨物の特性や納期、環境への配慮などを踏まえて、最適な輸送手段を選びましょう!主な輸送手段は、以下の通りです。
海上輸送
ハンブルク港を中心とした大量輸送向けのルートです。安定性に優れていますが、港湾混雑による遅延には注意が必要です。
航空輸送
フランクフルト空港経由が主流です。高価値品や短納期品に最適ですが、コストは高めになります。
鉄道輸送
中国発のシルクロードルートは約18日でドイツに到着します。詳細は「ポーランドの鉄道輸送戦略」で解説していますので、ぜひご覧ください。
最適な輸送手段を選ぶためには、貨物の特性、納期、CO₂排出量のバランスを踏まえた総合的な判断が求められます。
日EU・EPA協定の概要と原産地証明要件
日EU経済連携協定の第3章「原産地規則(Rules of Origin)」では、関税削減を受けるための明確な条件が定義されています。特に、原産性を立証するためには、製造工程や部品構成比率を明確に証明する必要があります。
証明方法の違いを理解する
特定原産地証明は商工会議所が発行するものであり、自己申告制度(REX)は輸出者登録を前提とします。REX番号を持たない企業が自己申告をすると、EPAの適用は無効です。
また、ドイツ税関ではEPA証明書のチェックが厳格に行われており、HSコードや記載形式の誤りによって審査の差戻しや課税が発生するケースが多く見られます。
ドイツ輸送を安定させる3つの実務チェック
ドイツ向け輸送を成功させるためには、以下の3点を必ず確認しましょう。
1. EPA証明書の正確性
HSコードと原産地基準が一致しているかを確認します。
2. トランジット書類(T1・T2)の精度
ロッテルダムやポーランド経由時に、誤記載がないかを再確認します。
3. 鉄道輸送のリスク対策
貨物保険、遅延時の代替輸送手段、連絡体制を明確化しておきます。
フォワーダー選定では、EPA知識・鉄道輸送の統合管理・遅延時の調整力を兼ね備えた業者が理想的です。
フォワーダー連携と日本側準備の強化
EPA証明・鉄道輸送の成功は、輸出者とフォワーダー間の情報共有精度と契約実務にかかっています。以下の流れを意識して運用しましょう。
書類準備の前倒し
インボイス・パッキングリスト・EPA証明は輸送前に共有し、予備審査で整合性を確認します。
契約締結時の確認事項
遅延・損害・再輸送・保険請求条件を明文化し、双方の責任範囲を明確にします。
通関後のフォローアップ
税関照会・EPA監査・VAT還付に関する対応責任者を事前に決定しておきます。
連絡フローの可視化
書類更新や貨物追跡情報を共有するための連絡チャネルを設けます。これらを仕組み化することで、EPA監査・再通関・遅延リスクにも迅速に対応できるようになります。
フォワーダー選定では、EPA知識・鉄道トレーサビリティ管理・環境対応力の3点を基準にするのが理想です。これらの具体事例は「ヨーロッパフォワーダー選定ガイド」で紹介していますので、併せてご参照ください。



